役員運転手にも36協定は適応?労働時間の扱いや注意点まで解説
2025年07月22日
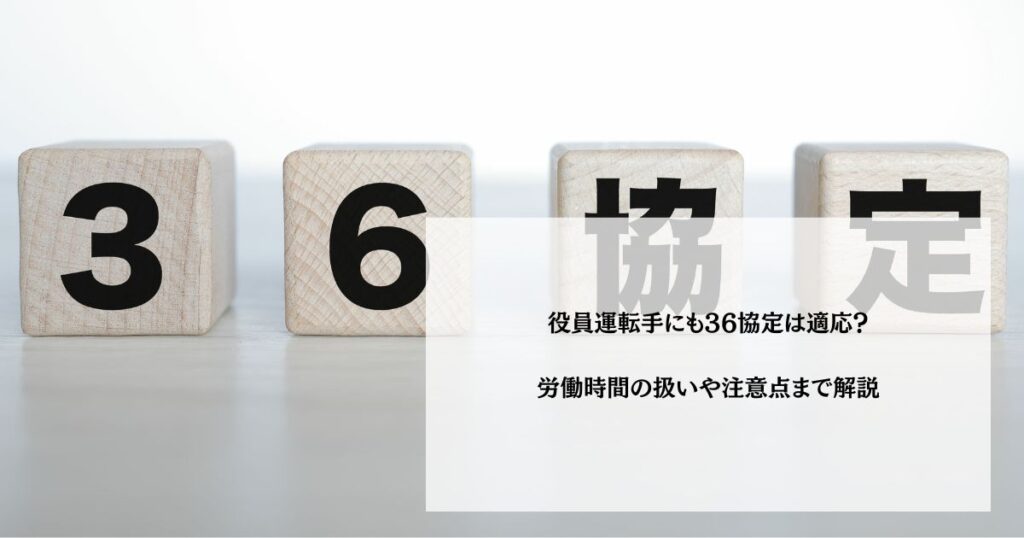
役員運転手は特殊な勤務形態であるため、36協定が必要か悩む担当者も多いのではないでしょうか。
結論として、役員運転手も労働基準法上の「労働者」であるため、原則として36協定の締結が必要です。
法定労働時間を超えて業務を命じる場合、協定なしでは法律違反となり罰則の対象となります。
ただし、役員運転手の業務実態に合わせて「断続的労働の適用除外制度」という例外規定が設けられています。
この記事では、役員運転手と36協定の関係を基本から整理し、適用除外制度を利用するための具体的な条件や申請方法、注意点をまとめました。
目次
1. 役員運転手に36協定は適用される?
役員運転手であっても、労働基準法上の「労働者」に該当する以上、36協定の締結が必要です。
36協定とは、労働基準法第36条に基づいて締結される労使間の協定で、法定労働時間を超える労働や休日労働を行うために必要な手続きです。
労働基準法では、1日8時間・週40時間を超えて労働させる場合、事前に36協定を締結し、労働基準監督署に届け出なければなりません。
ただし、役員運転手の場合は待機時間が長いため例外となる場合があります。
1-1. 待機時間の扱いには注意が必要
役員運転手の場合、待機時間の扱いが問題になることも多いでしょう。
待機時間中は、指示があれば即時対応が求められるため、原則として労働時間に含まれます。
しかし、労働基準法第41条には「断続的労働に従事する者」という規定の例外が定められており、役員運転手は該当する可能性があります。
役員運転手を雇用する際は、このような規定が設けられていることも併せて確認しておきましょう。
2. 断続的労働の適用除外制度とは
断続的労働の適用除外制度とは、待機時間が長い業務の場合に認められる可能性がある制度です。
申請が通れば、労働基準法の「労働時間」「休憩」「休日」に関する項目が適用されません。
具体的には、以下のような取り扱いになります。
1.労働時間の基準が適用されない
2.休憩時間の規定が適用されない
3.休日の規定が適用されない
4.時間外手当や休日手当の支払いが不要(深夜手当の支払いは必要)
ただし、断続的労働の適用除外制度は、必ずしも認められるわけではありません。
審査についても厳格で、労働基準監督署の許可が必要になります。
2-1. 断続的労働の適用除外制度を申請するための条件
断続的労働の適用除外制度を申請するためには、以下の3つの条件があります
2-1-1. 身体または精神的緊張の少ない業務であること
制度を利用するためには、身体または精神的緊張の少ない業務と認められる必要があります。
例えば、座ったまま監視をする仕事など、体力的・精神的に不安が少ない仕事です。
一般的な役員運転手の業務であれば、申請できる可能性も十分にあるでしょう。
2-1-2. 待ち時間が実作業時間を上回ること
次に、待機時間が実作業の時間よりも長くなることが必要です。
役員運転手においては、実際の運転時間が勤務時間の半分以下であれば断続的労働の適用除外制度の対象です。
例えば、1日8時間の勤務のうち実際の運転時間が3時間で、待機時間が5時間の場合は条件を満たします。
2-1-3. 実作業の合計時間が8時間を上回らないこと
役員運転手における「実作業」とは、実際に車を運転している時間を指します。
つまり1日に8時間以上の運転を行う場合、断続的労働の適用除外制度は対象外となります。
2-2. 断続的労働の適用除外を受けるためには許可が必要
断続的労働の適用除外を受けるためには上記の条件を満たす他に、労働基準監督署の許可が必要です。
申請に必要な書類は以下の3つがあります。
1.監視・断続的労働に従事する者に対する適用除外許可申請書
2.対象労働者の労働の態様が分かる資料
3.対象労働者の労働条件が分かる資料
許可を受けるためには、勤務実績や業務内容を詳細に示した書類審査、労働者本人への聴取など手間がかかることから、実際に適用除外許可を取得している企業は多くありません。
2-3. 深夜手当は支給が必要
断続的労働の適用除外制度において、時間外手当や休日手当の支払いは対象外となります。
ただし、深夜手当の支払いは必要です。
労働基準法では、22時から5時までの間に労働させた場合、通常の賃金の25%以上の割増賃金を支払わなければなりません。
これは断続的労働の適用除外制度においても同様の扱いとなります。
3. 役員運転手に36協定が必要になる条件
36協定の締結が必要になるのは、労働者に労働基準法で定められた基準以上の労働時間を課す場合が該当します。
具体的には以下の場合に36協定が必要です。
1.1日8時間を超える労働をさせる場合
2.週40時間を超える労働をさせる場合
3.休日に労働をさせる場合
また、断続的労働の適用除外制度の条件を満たしていない場合にも、36協定の締結が必要になります。
実際の運転時間が長い場合や、身体的・精神的緊張の大きい業務を行う場合は、通常の労働基準法が適用されます。
4. 役員運転手に36協定を締結しなかった場合の罰則
36協定が締結されていないのに、1週間に40時間を超えて労働をさせた場合は労働基準法違反です。
違反した場合の罰則は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金となります。
これらの罰則は、雇用者(会社)に対して科せられるものです。
労働基準法違反がある場合、従業員が労働基準監督署へ申告することも可能であり、実際に申告されるケースもあるため注意が必要です。
5. 役員運転手業務の外部委託を活用するケースも
自社で役員運転手を雇うのは負担が大きいと感じる場合には、外部委託を活用する方法もあります。
外部に委託すると、まずコスト削減と業務負担の軽減が可能です。
直接雇用の場合は、給与だけでなく社会保険料や各種手当も負担する必要があります。
しかし、外部委託であれば委託費用以外は基本的にかかりません。
また、36協定の締結や労務管理も委託先が行うため、自社の業務負担を大幅に削減できます。
さらに、教育システムの構築も不要になります。
運転技術や接客マナーの教育は、専門の委託業者が行うため、自社で研修制度を整備する必要がありません。
ただし、委託先の選定には注意が必要です。
適切な労務管理を行っている信頼できる業者を選ぶことで、安心して業務を委託できます。
特に、断続的労働の適用除外制度の条件を満たすことが難しい場合や、労働時間の管理が業務の負担になる場合は、外部委託の検討をおすすめします。
6. まとめ
役員運転手も労働者である以上、原則として36協定の対象となります。
ただし、断続的労働の適用除外制度により、労働時間・休憩・休日の規定が適用除外となれば、長時間の待機があっても残業代が発生しません。
この制度を利用するにはいくつかの条件を満たし、労働基準監督署長の許可が必要です。
36協定なしで法定労働時間を超えた場合は罰則があるため、適切な労務管理を行いましょう。
自社で役員運転手を雇うのは負担が大きいと感じる場合には、外部委託を活用する方法も検討することをおすすめします。
専門家に相談し、自社に最適な方法を選択してください。
カテゴリ:Contents


