役員運転手の直接雇用とは?派遣との比較やメリット、デメリットをご紹介
2025年11月21日
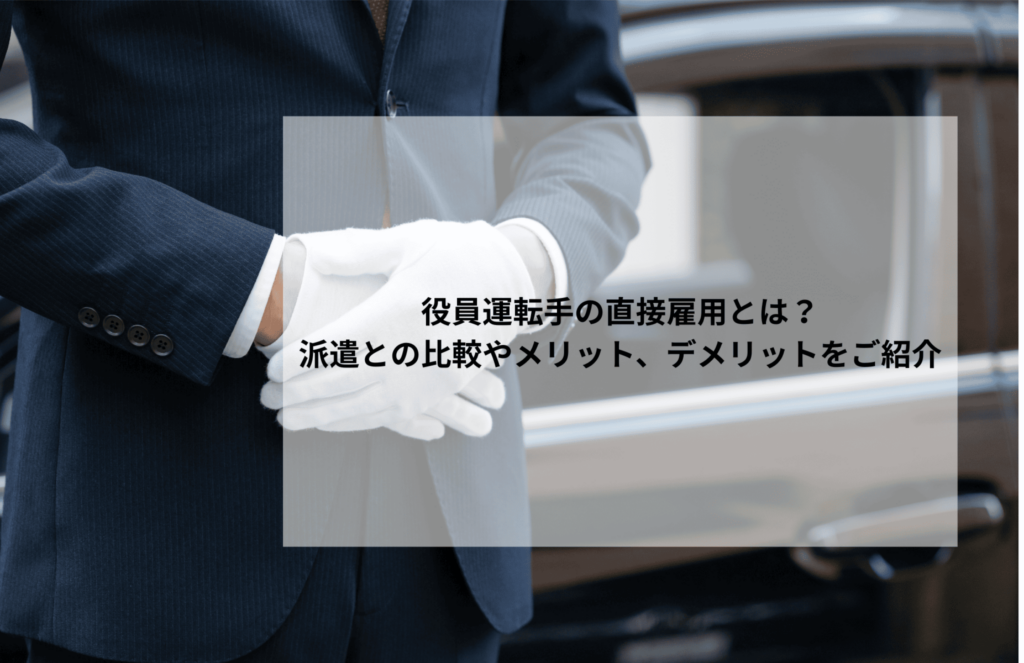 役員運転手の雇用を検討する際、「直接雇用と派遣どちらがよいのか」「コストや管理面で何が違うのか」と悩まれる方は多いでしょう。
役員運転手の雇用を検討する際、「直接雇用と派遣どちらがよいのか」「コストや管理面で何が違うのか」と悩まれる方は多いでしょう。
直接雇用は信頼関係を築きやすく、長期的な雇用が可能な一方で、育成コストや福利厚生の負担が発生します。
この記事では、役員運転手の直接雇用について派遣や外部委託との違い、メリット・デメリット、採用時のチェックポイント、育成方法、給与相場まで具体的に解説します。
自社に最適な雇用形態を選ぶための判断材料として、ぜひ参考にしてください。
目次
1. 役員運転手の直接雇用とは?
役員運転手の直接雇用とは、企業が運転手を正社員として直接雇う形態です。
派遣や外部委託と異なり企業が運転手と直接労働契約を結ぶため、給与や福利厚生も管理します。
役員運転手を雇うことで、役員は移動時間を効率的に活用できます。
企業の専属運転手となるため、同じ企業の役員や従業員の送迎を担当するのが一般的です。
また、給与は一般の社員と同様、月給制で支払われます。
さらに、企業が直接管理・指導できるため、自社の文化や方針に沿った育成が可能である点もメリットです。
2. 他の雇用形態との違い
役員運転手の雇用形態には、直接雇用のほかに派遣契約と外部委託があります。
それぞれの特徴を理解することで、自社に最適な方法を選択可能です。
コストや管理の手間、柔軟性などが異なるため、企業のニーズに応じて選択しましょう。
2-1. 派遣契約
派遣契約は、派遣会社を通じて専門の運転手を一定期間確保する方法です。
企業が直接雇用するのではなく、派遣会社が運転手と契約を結びます。
契約期間が明確に定められており、必要な期間だけ雇用できるのが特徴です。
短期間で即戦力を確保でき、労務管理の負担を軽減できます。
また、派遣会社が事前に運転技術やマナーも教育しているため、採用後すぐに業務を任せられます。
急な欠員や繁忙期の人員補充にも迅速に対応できるのが大きな利点です。
そのため、特定プロジェクト期間など、一時的に運転手が必要な場合に適しているでしょう。
ただし、労働者派遣法により同一部署での勤務は最長3年までと制限されています。
3年経過後は直接雇用に切り替えるか、別の派遣スタッフとの契約が必要です。
派遣契約は直接雇用と比べて運用面の柔軟性は高いものの、長期的な信頼関係の構築は難しい側面があります。
さらに、費用面では、派遣会社への支払いが発生するため、長期的には割高になることもあります。
運転手の外注に関しては以下の記事でも解説していますので、あわせてご覧ください。
2-2. 外部委託(請負)
外部委託は、請負会社と契約を結ぶ方法です。
仕事に関する指揮命令は請負会社が行うため、企業は運転手に直接指示を出せません。
運転手の労務管理や残業管理を一括で任せられるのが大きなメリットです。
また、交通事故などのトラブルが発生した場合も、請負会社が対応してくれます。
社会保険や福利厚生の手続きも請負会社が行うことにより、人事部門の業務軽減が可能です。
人事や労務管理の負担を大幅に削減できるため、管理コストを抑えたい企業に向いています。
ただし、行き先の指定など細かい指示ができません。
くわえて、企業と運転手の間に請負会社が入るため、直接のやり取りが難しく、スケジュール変更や緊急対応の際に時間を要する場合があります。
運転業の依頼に関しては以下の記事でも解説していますので、あわせてご覧ください。
3. 役員運転手を直接雇用するメリット
直接雇用には、派遣や外部委託にはないメリットがあります。
ここでは、直接雇用ならではのメリットを詳しく見ていきましょう。
3-1. 信頼関係を構築しやすい
直接雇用では、企業と運転手が長期的に関係を構築可能です。
毎日顔を合わせることで、役員と運転手の間に深い信頼関係も生まれるでしょう。
また、直接雇用の運転手は企業の一員として働くことで、企業の文化や価値観を深く理解し、日々の業務にも反映することができます。
さらに、役員の好みや習慣を把握することで、より質の高いサービス提供が可能になるでしょう。
派遣や外部委託では人が代わることもありますが、直接雇用なら継続的なサービスが可能です。
信頼関係が深まると、役員も気持ちよく車内で仕事や会話ができるようになり、企業秘密や重要な情報を扱う場面でも、長年の信頼があれば安心して任せられます。
このような信頼関係は、短期契約の派遣や外部委託では得られにくいメリットでしょう。
3-2. 運転業務以外も依頼できる
直接雇用の運転手は待機時間中も給与が発生するため、別の業務も依頼できます。
具体的には、オイル交換などの定期的なメンテナンスや、洗車などの車両管理も任せられます。
例えば社内の書類配達や備品の運搬のほか、秘書業務のサポートとしてスケジュール管理や資料準備などの依頼も可能です。
また、来客時の受付対応や、会議室の準備などを依頼できるケースもあります。
多様な業務を任せることで、人材の効率的な活用が可能です。
待機時間を有効活用できるため、企業にとってもコストパフォーマンスが向上するでしょう。
3-3. 長期的な雇用ができる
直接雇用では、企業の専属として長期間働いてもらえます。
派遣スタッフの場合、労働者派遣法により同一部署での勤務は3年までと制限されています。
直接雇用ならこうした制限がなく、定年まで勤務してもらうことも可能です。
長期雇用により経験を積むことで、役員の細かいニーズにも対応できるようになり、将来的に運転業務が不要になった場合も、別の部署に配置転換できます。
企業側も長く働いてもらうことで、採用コストや教育コストも削減可能です。
人材の入れ替わりが少ないため、サービスの質が安定し、役員の満足度も高まるでしょう。
3-4. スケジュールに柔軟に対応できる
会議時間の延長や突然の来客による予定変更にも、直接雇用なら臨機応変に対応できます。
役員の予定は頻繁に変更されるため、柔軟な対応が求められます。
例えば、早朝や深夜の送迎が必要になった場合でも、調整しやすいのが特徴です。
また、派遣や外部委託は契約内容に縛られますが、直接雇用なら企業から指示ができ、緊急時の対応や休日出勤の依頼も相談しやすいといえます。
スケジュール変更の連絡も直接行えるため、迅速な対応が可能です。
派遣や外部委託では変更のたびに会社を通す必要があり、時間がかかることもあるでしょう。
しかし直接雇用なら、役員と運転手が直接コミュニケーションを取れるため、無駄がありません。
4. 役員運転手を直接雇用するデメリット
役員運転手の直接雇用には注意すべき点もあります。
事前にデメリットを理解し、対策を考えておくことが重要です。
4-1. 育成コストがかかる
運転技術やマナーの向上には、継続的な研修が必要であり、育成コストがかかります。
例えば、運転技術の研修以外に、ビジネスマナーや守秘義務に関する教育も実施しなければなりません。
また、人事担当者が研修プログラムを組み、指導する負担も大きくなります。
さらに、先輩運転手の時間を割いて指導する必要があり、その分の人件費も発生します。
ただし、長期的に見れば自社で育成した方が企業文化に馴染みやすく、結果的にコストパフォーマンスも高まるでしょう。
4-2. 福利厚生などの費用がかかる
直接雇用では、運転手の厚生年金や雇用保険、労災保険など、法定福利費がかかり、会社にとって大きな負担となります。
会社によっては、社宅が用意されているところもあります。
これに対し、外部委託の場合は業者に支払う費用のみで済むため、福利厚生の負担はありません。
ただし、退職金などの福利厚生が充実していれば長期的に優秀な人材を確保しやすくなります。
それにより、運転手のモチベーションも高まり、長期的には企業にとってプラスに働きます。
コストと効果のバランスを考えて、判断することが大切です。
5. 役員運転手を直接雇用する際の注意点
直接雇用を成功させるには、採用時にいくつかのポイントをチェックする必要があります。
適切な人材を見極めることが、長期的な信頼関係の構築につながります。
5-1. 必要な運転技術は身についているか
役員を乗せて運転するには強い責任感が求められ、同時に高い運転技術が不可欠です。
安全を最優先に、事故を防ぐための丁寧で安定した運転が求められます。
役員は車内で仕事をすることも多いため、急ブレーキや急ハンドルを避け、スムーズに走行する技術も必要です。
また、主要な道路や渋滞しやすいルートの把握も重要なポイントです。
さらに、時間帯による交通状況の変化を理解し、最適なルートを選択できる能力が求められます。
必要に応じて、採用前に実技試験を行い、運転技術を確認することも重要です。
5-2. ビジネスマナーが備わっているか
役員運転手には、高いビジネスマナーが求められます。
他の役員や取引先と接触する機会も多く、礼儀正しい対応が必要です。
敬語の使い方や挨拶の仕方、名刺交換のマナーなど、失礼のないように基本的なビジネススキルは必須です。
また、服装や身だしなみにも気を配り、企業の顔としてふさわしい印象を与えることが大切です。
そして、常に清潔感のあるスーツを身につけ、靴はしっかりと手入れされていることが求められます。
役員の代わりに荷物を運んだり来客対応をしたりすることもあるため、細やかな気配りができる人材かどうかを面接で見極めましょう。
5-3. コミュニケーション力があるか
役員運転手として理想的なのは、必要なときに適切なコミュニケーションが取れる人材です。
例えば、車のドアの開閉や荷物のサポートなど、細やかな気配りが求められます。
役員の表情や様子から気持ちを読み取り、適切に対応する力も重要です。
さらに、疲れている様子なら静かに運転し、話したそうなら適度に会話に応じるなど、空気を読む力も必要です。
役員がリラックスできる雰囲気を作りつつ、必要なコミュニケーションが取れる人材であることが望ましいでしょう。
また、取引先の方と話をする場合など、失礼のないような話し方や言葉遣いを身につけている必要があります。
5-4. 守秘義務を守れるか
役員運転手には厳格な守秘義務があり、絶対に外部に情報を漏らしてはいけません。
車内では、役員同士の会話や電話で重要な情報を耳にすることもあるでしょう。
些細な情報でも、口外すれば大きなトラブルに発展する可能性があります。
信頼できる人物かどうかを見極めることは、企業の信用と安全を守るうえで欠かせません。
また、定期的に研修を実施し、守秘義務に関する意識を継続的に高めていくことも重要です。
6. 役員運転手を育成するための具体的な取り組み
採用後の育成も、直接雇用を成功させる重要なポイントです。
計画的な研修を実施することで、質の高いサービスを提供できます。
6-1. 運転技術の研修
役員運転手の育成において、運転技術の研修は欠かせません。
役員は車内で仕事をすることも多いため、揺れの少ない安定した運転技術が重要です。
また、先輩運転手に同乗してもらうことで、自分では気づきにくい癖や改善点も客観的に指摘してもらえます。
さらに、安全運転だけでなく、主要な目的地までの複数のルートを覚え、状況に応じて使い分ける能力も必要です。
毎日、分刻みのスケジュールで動いている役員に合わせて、取引先との仕事に支障をきたさないよう、合理的な運行ルートを提案できるようにしましょう。
時間帯や曜日による交通状況の違いを把握し、事故を起こさないようにする運転技術も重要です。
国土交通省で公開している安全教育・事故防止マニュアルを活用する方法もよいでしょう。
6-2. マナーや守秘義務の教育
マナーと守秘義務は、役員運転手として最も重要な要素です。
他の役員や取引先と接触する機会も多いため、挨拶の仕方、言葉遣い、電話対応など、基本的なマナーの教育は必須です。
スーツの着こなしや靴の手入れなど、身だしなみに関する研修の実施も効果的といえるでしょう。
企業の印象を左右するため、細部まで整える姿勢が求められます。
守秘義務に関しては、入社時だけでなく定期的に研修を行う必要があります。
具体的な事例を用いて、どのような情報が漏洩のリスクになるかを共有しましょう。
情報が漏れた場合の影響の大きさを伝え、責任感を持って仕事に取り組むよう促します。
7. 直接雇用した際の給与相場は?
役員運転手を直接雇用する場合、平均年収は400万円ほどです。
経験やスキル、企業規模によって幅がありますが、一般的なサラリーマンと同程度の水準です。
土日祝日の勤務手当や、勤務時間外の送迎が残業代として支給される企業もあり、残業代を含めると、実際の年収はさらに高くなることもあります。
また、退職金や福利厚生が充実していれば、給与以外の面でも魅力的な条件を提示できます。
社宅や住宅手当、家族手当などがあれば、実質的な待遇はさらに向上するでしょう。
一方、外部委託の場合は月額40〜60万円ほどの費用がかかります。
年間ベースで考えると直接雇用よりも高額になるケースが多いです。
派遣の場合も、派遣会社への支払いが月額50万円前後になることがあります。
長期的なコストを考えると、直接雇用の方が経済的なメリットがあるといえるでしょう。
8. まとめ
役員運転手の直接雇用は信頼関係を構築しやすく、柔軟な対応や長期雇用がしやすい点がメリットです。
一方で、育成コストや福利厚生の負担がかかるといったデメリットもあります。
派遣契約の場合は、即戦力の人材を必要なタイミングで迅速に確保できる点がメリットですが、契約期間に限りがあることに注意が必要です。
また、外部委託は、労務や人員管理の手間が少なく即戦力を確保しやすいものの、運用や対応面での柔軟性に欠け信頼関係を構築しにくい傾向にあります。
この記事を参考に自社のニーズや予算、求めるサービスレベルを考慮して最適な雇用形態を選びましょう。
長期的な信頼関係を重視するなら直接雇用、即戦力をすぐに確保したい場合は派遣契約が適しています。
運用負担を減らし効率的に人員を確保したい場合は外部委託が有効な選択肢となるでしょう。
カテゴリ:Contents


